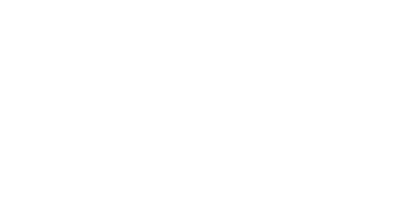研究活動の検索
研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。生命機能工学領域の藤本教授らの研究チームが超高速遺伝子解析用試薬の実用化に寄与
生命機能工学領域の藤本健造教授らの研究チームは、 日華化学株式会社(本社:福井市、代表取締役社長:江守康昌、以下日華化学)と共同研究を行い、同研究室の保有する研究成果と、日華化学のコア技術である精密有機合成の知見を生かし、超高速遺伝子解析用試薬の安定供給・品質の確保を実現しました。
この試薬は、藤本教授らが発明者である基本特許を使用しており、国内外の研究者や企業から多くの問合せを受けていました。今回、日華化学との共同研究を通じて、合成プロセスの改良により大幅なコストダウンと安定供給を実現したものです。今後、国内外の研究者や企業での利用、応用が期待されます。
■研究概要
藤本研究室では、光を用いて遺伝子を操作する全く新しい独自の技術を追求しています。藤本教授が開発した核酸試薬を用いることで、DNAを自在に光で高速操作できるようになり、高速遺伝子解析が可能となるだけでなく、細胞内の遺伝子発現を光制御できるようになりました。研究室では、これからも医療・健康分野に焦点を当てながら、生命科学の枠を超えて様々な分野への貢献を目指し研究を進めています。
■今後の展開
光を用いた核酸類操作は、従来の酵素を用いた遺伝子操作と比較して操作性、機械化への適用度、コスト、時空間制御といった点で優れていると考えられます。LED光を照射した時だけ、照射した場所にのみ操作でき、しかも誰もがスイッチ1つで操作可能なユーザーフレンドリーな技術として期待されています。細胞内での遺伝子発現制御にも最近有効であることが見出されており、手軽な遺伝子診断システムをはじめ、局所疾患への医療応用など幅広い分野への貢献が期待されます。
日華化学株式会社プレスリリース
http://www.nicca.co.jp/01topics/2016/09/post-194.html
平成28年9月15日
出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/09/15-1.html物質化学領域の松村准教授らの研究成果が英国王立化学会発刊Nanoscale誌のback coverに採択
物質化学領域の松村和明准教授らの研究成果が英国王立化学会発刊Nanoscale誌のback coverに採択されました。
■掲載誌
英国王立化学会(Royal Society of Chemistry) Nanoscale(インパクトファクター7.76) 2016, 8, 15888-15901
■著者
Sana Ahmed (D3), Satoshi Fujita (福井大学), Kazuaki Matsumura*
■論文タイトル
Enhanced protein internalization and efficient endosomal escape using polyampholyte-modified liposomes and freeze concentration
■論文概要
細胞質に物質を導入する技術は、ドラッグデリバリーシステムの効率化において重要な技術である。一般的には細胞膜を容易に通過出来ないため、様々な手法が検討されてきている。本論文では、細胞懸濁液を凍結することによって起こる凍結濃縮現象を利用し、細胞周囲に、細胞内へ導入したいタンパク質を濃縮させ、取り込み向上を図ったものである。その際、タンパク質のナノキャリアとして両性電解質高分子で修飾されたリポソームを用いることで、取り込み後の細胞質内への効率的移動も確認出来た。この技術により、抗原を細胞質内へ高効率で送達することで免疫細胞を活性化する免疫療法に応用できるだけでなく、遺伝子を核内に導入する遺伝子治療への応用も期待出来る。
本研究は科研費挑戦的萌芽研究(15K12538、 16K1289)および本学のソフトメゾマター研究拠点(代表濱田勉准教授)の成果です。
論文詳細: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nr/c6nr03940e#!divAbstract

平成28年9月5日
出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/09/05-1.html日本海イノベーション会議[北陸先端科学技術大学院大学プログラム]を開催

8月27日(土)、日本海イノベーション会議[北陸先端科学技術大学院大学プログラム](本学、北國新聞社主催)が開催されました。
「日本海イノベーション会議」とは、石川県内の大学の研究成果等を広く県民や企業に知ってもらうことを目的として、北國新聞社と石川県内の大学が共同で開催している講演会であり、今年度は、「先端科学技術が拓く未来」をテーマに、寺野 稔理事・副学長と先端科学技術研究科(物質化学領域)の山口 政之教授が約60名の聴講者を前に講演を行いました。
第1部では寺野理事が「未来を拓くプラスチック」と題して、最先端の科学技術が身近なプラスチックに数多く応用されていることを、医療器具、自動車部品、食料品等を例に、わかりやすく解説しました。
第2部では山口教授が「知性を備えたプラスチック」と題して、「インテリジェント(知性を備えた)な高分子」と呼ばれる、外部の環境に応じて形態を変えるプラスチックやゴムに関する研究について、フィルムの透明度が温度によって変化する様子など、映像も交えて紹介しました。

寺野理事

山口先生

講演会の様子
平成28年8月29日
出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/08/29-2.html生命機能工学領域の平塚准教授らの共同研究がNEDO「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」に採択
生命機能工学領域の平塚祐一准教授が参画する研究課題が、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」に採択されました。
NEDOは、2015年に策定された政府の「ロボット新戦略」を受け、2015年度から「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」を推進しています。このプロジェクトは、現在のロボット関連技術の延長上に留まらない、人間の能力を超えることを狙った革新的な要素技術をターゲットとし、これまで人工知能・ロボットの導入を考えもつかなかった未開拓の分野で、新しい需要を創出することを狙っています。
NEDOは、次世代の人工知能・ロボットの研究開発強化に向けて、「次世代人工知能技術分野」および「革新的ロボット要素技術分野」において、今まで実現されていない革新的な要素技術をターゲットに公募を実施し、今回、13テーマを採択しました。
■採択期間
平成28年度~平成29年度(継続の可能性あり)
■研究課題
「生体分子を用いたロボットの研究開発」
■共同研究機関
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
国立大学法人東京工業大学
国立大学法人北海道大学
詳しくはNEDOホームページをご覧下さい。
http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100599.html
平成28年7月19日
出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/07/19-1.html学生の Gargi Joshiさんの論文が英国王立化学会刊行 Soft MatterのBack Coverに採択
学生のGargi Joshiさん(博士前期課程2年、環境・エネルギー領域・金子研究室)の論文が、英国王立化学会刊行 Soft MatterのBack Coverに採択されました。
■掲載誌
Royal Society of Chemistry, Soft Matter 2016, 12, 5515 - 5518.
■著者
Gargi Joshi, Kosuke Okeyoshi*, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko*
■論文タイトル
Directional control of diffusion and swelling in megamolecular polysaccharide hydrogels
■論文概要
3次元網目構造を持つ高分子ゲルは生体組織に類似する特徴を多々有しており、新規バイオマテリアルへの応用が注目されています。通常のゲルでは等方的に体積膨潤するのに対し本研究では、内部の層構造を制御することで異方的に膨潤するハイドロゲルの作製に成功しました。100倍以上の膨潤率を示すこのゲルは、水の拡散吸収が層構造の側面から起こり、層間隙を広げて一軸方向にのみ膨潤する特徴が実証されました。高分子ネットワークはシアノバクテリア由来の超高分子量を持つ多糖類「サクラン」で構成され、高分子の自己配向性・生体適合性・高吸水性などを有します。水の拡散と膨潤方向が制御されたゲルの特性を活用することで、ティッシュエンジニアリング・再建手術・ドラッグデリバリーシステムなど医療用材料への展開が期待されます。
参考 http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/sm/c6sm00971a#!divAbstract
平成28年6月23日
出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/06/23-1.html物質化学領域の松見教授らの研究成果が英国王立化学会 Polymer ChemistryのBack Coverに採択
物質化学領域の松見紀佳教授らの研究成果が英国王立化学会 Polymer ChemistryのBack Coverに採択されました。
■掲載誌
英国王立化学会 Polymer Chemistry, 2016, 7, 4182 - 4187
■著者
Puhup Puneet, Raman Vedarajan, Noriyoshi Matsumi*
■論文タイトル
σ-p Conjugated Copolymers via Dehydrocoupling Polymerization of Phenylsilane and Mesitylborane
■論文内容
共役系高分子は高分子エレクトロニクスの中核を担う重要な材料群である。初期の共役系材料として白川らによるπ-共役系ポリアセチレンの発見、Burkhardらによるσ-共役系ポリシランの創出が挙げられるが、それらは更にσ-π共役系有機ケイ素高分子(櫻井、熊田ら)、p-π 共役系有機ホウ素高分子(中條、松見ら)など、ヘテロ元素を含んだユニークな軌道間相互作用を活用した共役系高分子の創出につながっている。
今回、従来にない共役モードによる新規共役系高分子としてヒドロシランとヒドロボランとの共重合によりσ-p共役系高分子と呼べる一連の高分子を合成した。それらの分光学的特性に加えて、オリゴマーモデルのDFT計算によってσ-p共役的軌道間相互作用が支持された。得られた材料は従来にない電子状態を有した共役系高分子としてそれらの特性に興味がもたれる。例えば、μMオーダーのフッ化物イオンの存在下で蛍光が増大するなど、turn-on型フッ化物イオンセンシング材料としての可能性が示された。
参考 http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/PY/c6py00205f#!divAbstract

平成28年6月22日
出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/06/22-2.html学生のNikolaos Matthaiakakisさんの共同研究成果論文がScientific Reports誌に掲載

学生のNikolaos Matthaiakakisさん(サウサンプトン大学物理科学・工学部・ナノグループ/博士課程3年、英サウサンプトン大学との博士協働研究指導プログラム第一期生、環境・エネルギー領域・水田研究室)の共同研究成果論文がScientific Reports誌(IF 5.578)に6月9日オンライン掲載されました。
本学と英国サウサンプトン大学の物理科学・工学部は、2013年9月に博士協働研究指導プログラム協定を締結し、博士課程の2年次で相手側大学に1年滞在して共同研究を行う日⇔英双方向での学生派遣を実施しています。Nikolaos Matthaiakakisさんはこのプログラムの第一期生として、昨年7月より環境・エネルギー領域/水田研究室に在籍しています。
Scientific Reports は、ネイチャー・パブリッシング・グループ(NPG)によって2011年6月に創刊された自然科学(生物学、化学、物理学、地球科学)のあらゆる領域を対象としたオープンアクセスの電子ジャーナルです。Thomson Reuters が2015年に発表した2014 Journal Citation Reportsでは、Scientific Reportsのインパクトファクターは5.578です。
■掲載誌
Scientific Reports誌(IF 5.578)
■論文タイトル
「Strong modulation of plasmons in Graphene with the use of an Inverted pyramid array diffraction grating(逆ピラミッド型回折格子を用いたグラフェン内プラズモンの強い変調)」
■論文概要
シリコン基板に逆ピラミッド型孔を周期的に形成したアレイ構造を、2次元原子材料グラフェン膜で覆うことで、表面プラズモン(物質の表面に局在して発生する電子の集団的振動)の波長と吸収を電気的に高効率で変調できる現象を理論的に見出しました。さらに、グラフェン膜上にイオン性液体ゲートを備えることで、グラフェンの化学ポテンシャルの変調効率を高め、プラズモン励起を電気的にスイッチオン・オフさせることも可能であることもわかりました。
■掲載にあたって一言
今回の研究成果は理論解析の範囲ですが、この原理が実験的に検証されれば、将来のオンチップ光変調器、光ロジックゲート、光インターコネクト、さらに光センサーなど幅広い応用展開が期待されます。現在、応用物理学領域/村田研究室のご協力をいただきながら素子作製を進めており、英サザンプトン大学との連携も最大限に利用して研究を加速していきたいと思います。
参考:*N. Matthaiakakis, H. Mizuta and M. D. B. Charlton, Scientific Reports 6:27550 DOI: 10.1038/srep27550
 水田研究室:中央 Nikolaos Matthaiakakisさん、中央左 水田教授
水田研究室:中央 Nikolaos Matthaiakakisさん、中央左 水田教授
平成28年6月15日
出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/06/15-1.html応用物理学領域の安准教授が村田学術振興財団の研究助成を採択
応用物理学領域の安東秀准教授が公益財団法人村田学術振興財団の研究助成を採択しました。
公益財団法人村田学術振興財団は、エレクトロニクスを中心とした科学技術の向上発展、及び国際化にともなう人文・社会科学的諸問題の解決に寄与するため、学術の研究に対する助成、学術的国際交流への助成等の諸事業を行い、わが国の学術研究の発展に寄与しようとするものです。
■採択期間
平成28年7月-平成29年7月
■研究課題
「NV中心ダイヤモンドロッドを用いた走査スピンプローブセンサーの開発」
■研究課題概要
ダイヤモンド中に存在する窒素-空孔複合体中心(NV中心)を走査型の磁場センサーとして用い、ナノスケールで磁気イメージングが可能な装置を開発する。特に、ダイヤモンドをレーザーカッティングの手法を用いて簡便に切り出す手法を考案すること。これを原子間力顕微鏡のプローブ先端に取り付け、共焦点顕微鏡と複合化し、簡便、且つ、高性能な装置を実現する。
■採択にあたって一言
この度は本研究助成に採択頂き、大変光栄です。村田学術振興財団および選考委員の皆様に御礼申し上げます。また、研究に貢献してくれている研究室メンバーに感謝いたします。
平成28年6月13日
出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/06/13-1.html環境・エネルギー領域の桶葭助教が三谷研究開発支援財団の研究開発助成に採択
環境・エネルギー領域の桶葭興資助教が三谷研究開発支援財団の研究開発助成に採択されました。
三谷研究開発支援財団は、財団法人三谷育英会の姉妹財団として、平成17年3月10日に設立され、今年で11年目を迎えました。三谷育英会は、三谷産業株式会社を創業した故 三谷進三氏の個人資産を基に、1960年設立され、以来、高等学校並びに大学に学ぶ学生に対し奨学金による支援が続けられております。2005年、三谷育英 会の設立45周年に際し、当時、三谷育英会の二代目理事長であった三谷美智子氏は「三谷育英会の奨学生が学ぶ大学の研究室で進められる研究開発に対しても、何か支援することが出来ないか」と思い、自身の持つ三谷産業株式会社株式200万株等を基に当財団を設立いたしました。当財団は、将来を担う研究者の 方に更に研究に邁進していただくため、石川県内の大学および大学院で行われている有益な研究に対し援助することを目的としています。なお、平成24年4 月より当財団は石川県の認定を受け、財団法人から公益財団法人へ移行し、新たな第一歩を踏み出しました。当財団は、石川県地域に立地する研究機関、すなわ ち大学及び大学院で行われている研究開発に対し、支援、表彰等を行い、もって地域の研究開発と産業の発展に寄与することを目的とします。
■採択期間
平成28年度
■テーマ
「乾燥誘起による超高分子多糖類の一軸配向膜作製技術の開拓」(天然高分子機能創発チーム)
■テーマ概要
自然界の生命が常に対面している乾燥現象を利用して、自然法則に基づいた高分子配向制御法の新機軸を構築する。特に、シアノ バクテリア由来高分子多糖類の水溶液の乾燥過程に着目し、高秩序化された高分子膜の作製技術を開拓する。乾燥による一軸配向膜作製の新たな技術を確立することで、細胞足場材料など医療分野や分子認識材料など環境分野への応用が期待できる。産業界においても高秩序化されたバイオ分子修飾基板の作製は、IPS 細胞培養用はじめ早急に解決すべき問題である。
■採択にあたって一言
本研究課題について採択頂き大変嬉しく存じます。三谷研究開発支援財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また、金子達雄教授はじめ、共同研究者の皆様、ご助言頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。科学と技術の発展に貢献できる様誠心誠意励んで参ります。
平成28年6月6日
出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/06/06-1.html